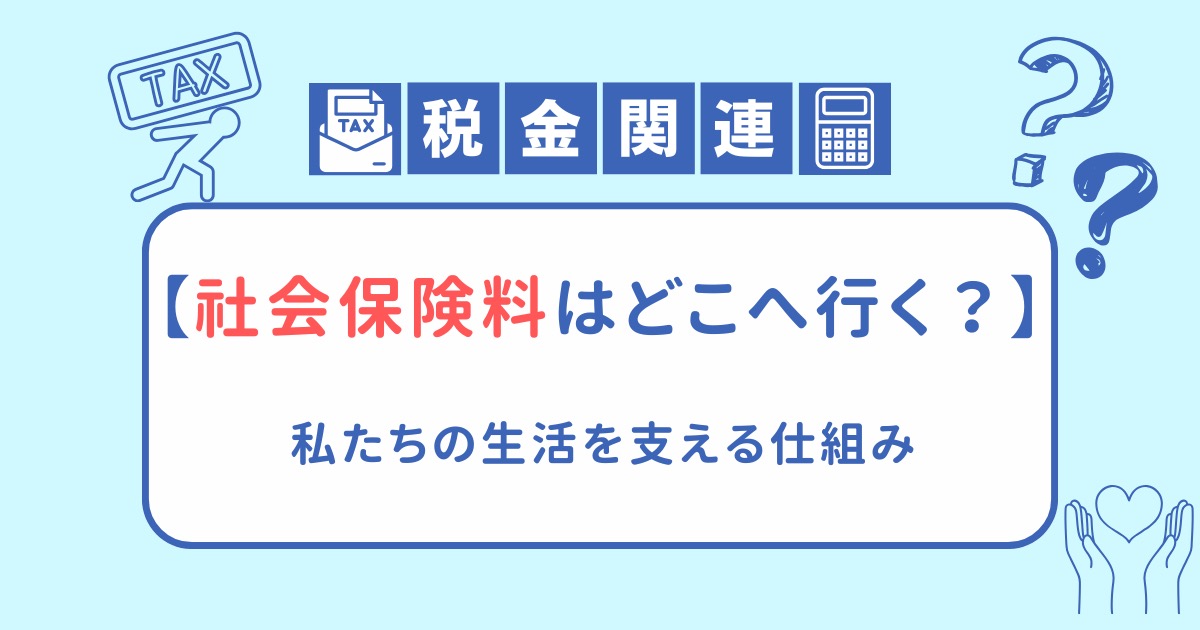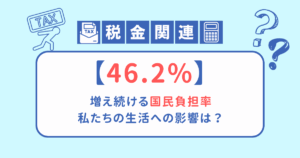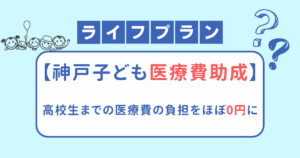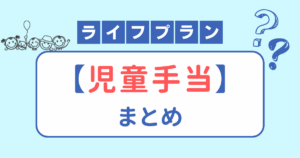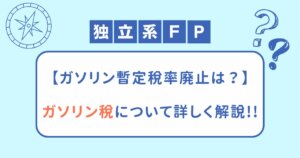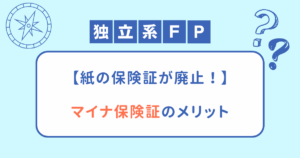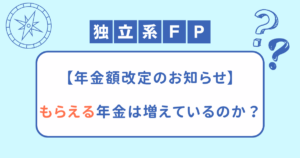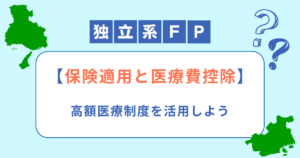こんにちは!
ここ数年、社会保険料が高いという声をよく聞きます。
今日は、その社会保険料が何に利用されているのかを見ていきたいと思います。

社会保険料について見ていきましょう
読んで欲しい人
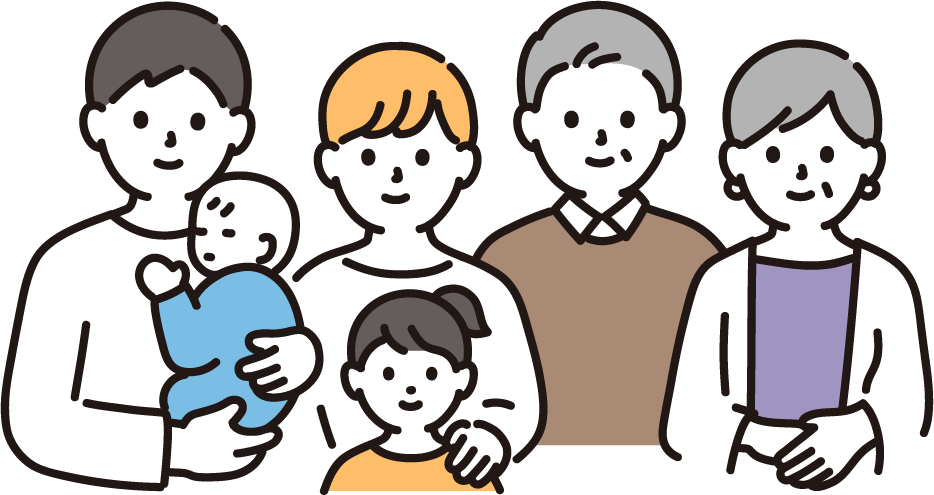
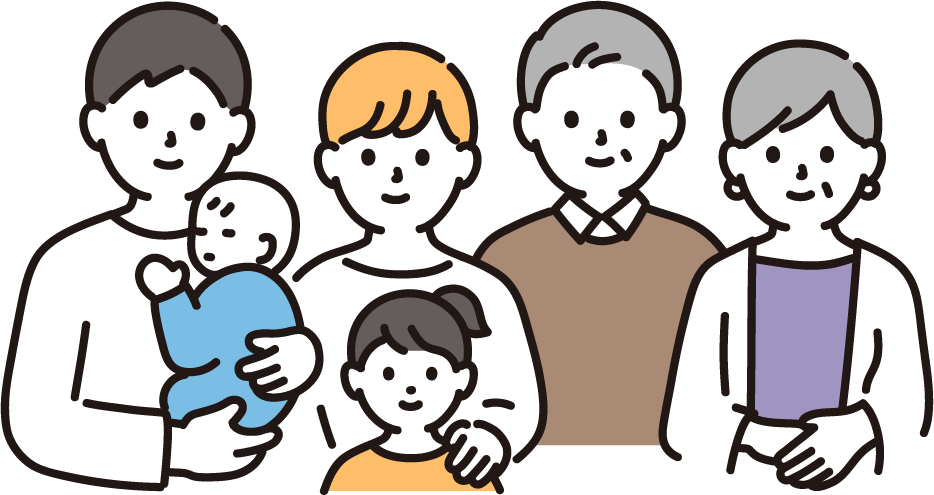
- 税金について知りたい方
- 社会保険を知りたい方
- 金融知識を深めたい方
はじめに
給与明細を見ると、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金」、「雇用保険」などの社会保険料が毎月しっかり差し引かれているのが見て取れます。
手取りが減るため負担感は大きいですが、そのお金はどこへ行き、どんな役割を果たしているのでしょうか。
今回は、社会保険料の使い道を整理してみます。



給与の約15%が社会保険料になります
社会保険料とは
社会保険料は、病気やケガ、失業、老後など、生活上のリスクに備えるための保険制度を運営するために徴収される費用です。
日本の社会保険は「相互扶助」の考え方に基づいており、現役世代が支払った保険料は、同時期に給付を受ける人の生活を支える仕組みになっています。



医療や年金の保障を充実させる制度です
主な社会保険制度と使い道
健康保険
医療費の一部負担(3割)で病院にかかれるのは、健康保険のおかげです。保険料は、病院や薬局への医療給付、出産手当金、傷病手当金などに使われます。高額療養費制度も健康保険の一部で、医療費が高額になった場合の自己負担を抑えます。
介護保険
2000年(平成12年)からスタートした比較的新しい制度です。40歳以上から支払う介護保険料は、介護が必要になった人への介護サービス(在宅介護、施設介護など)の費用に充てられます。急速な高齢化により介護給付費は年々増加しています。
厚生年金保険
現役世代が支払う厚生年金保険料は、老齢年金、障害年金、遺族年金として受給者に支払われます。積立方式と賦課方式を組み合わせており、将来の自分の年金だけでなく、現在の受給者の生活を支えています。
雇用保険
失業した場合の失業手当や、育児休業給付金、職業訓練の支援などに使われます。企業の雇用維持を目的とした助成金にも活用されています。
労災保険
仕事中や通勤中の事故によるケガ・病気に対する医療費や休業補償、障害・遺族補償に充てられます。全額事業主負担で、労働者からは天引きされません。
社会保険料の財源構造
社会保険の財源は、大きく分けて以下の3つです。
- 被保険者(労働者)の保険料
- 事業主(企業)の保険料負担
- 国庫(税金)による負担
制度によって負担割合は異なりますが、多くの場合は労使折半で、国も一定割合を負担しています。
例えば厚生年金では、労働者と事業主が半分ずつ保険料を負担しています。
家計への影響と見直しのヒント
社会保険料は手取り収入を減らす要因ですが、その分、病気や失業、老後のリスクを大幅に減らす「保険」でもあります。
ただし、保険でカバーされない部分(例えば先進医療や年金額の不足)は、自助努力で準備が必要です。
家計見直しでは、社会保険料そのものを減らすのは難しいです。
そのため、所得控除を活用して所得税・住民税を減らすことを考えましょう。



保険料控除・扶養控除・医療費控除など忘れずに申告しましょう
また、年金ネットでは将来の年金額が試算できるので、シミュレーションしてみましょう。
そして年金だけでは足りない分を、NISAやiDeCoなどのつみたて投資で補填するのが良いかもしれません。
まとめ
社会保険料は単なる「引かれるお金」ではなく、病気、介護、老後、失業など、人生のさまざまなリスクに備えるための社会的な仕組みを支えています。
制度の内容と使い道を理解しておくことで、家計管理や将来設計にも役立ちます。
毎月の天引きの意味を知れば、少し見方が変わるかもしれません。
少子高齢化がますます進む日本では社会保険料の減額はなかなか出来ないと思います。
ですが、働き方やちょっとしたテクニックで社会保険料を抑えることが出来る可能性もあるのでぜひ社会保険制度について知識を深めていきましょう。
参考資料